「北京のアダムスミス」(21世紀の諸系譜)続
ジョヴァンニ・アリギ著、2011年発行(翻訳)作品社
この本には付録があり、
1、資本の曲がりくねった道、デヴィット・ハーヴェイによるアリギへのインタビュー
2、資本主義から市場社会へ、北京のアダム・スミスに寄せて、山下範久氏の論文があり二つ合わせても80ページ近い分量である。
“続、資本主義のゆくへ、再論” の続きを読む
自分なりの読み方
「北京のアダムスミス」(21世紀の諸系譜)続
ジョヴァンニ・アリギ著、2011年発行(翻訳)作品社
この本には付録があり、
1、資本の曲がりくねった道、デヴィット・ハーヴェイによるアリギへのインタビュー
2、資本主義から市場社会へ、北京のアダム・スミスに寄せて、山下範久氏の論文があり二つ合わせても80ページ近い分量である。
“続、資本主義のゆくへ、再論” の続きを読む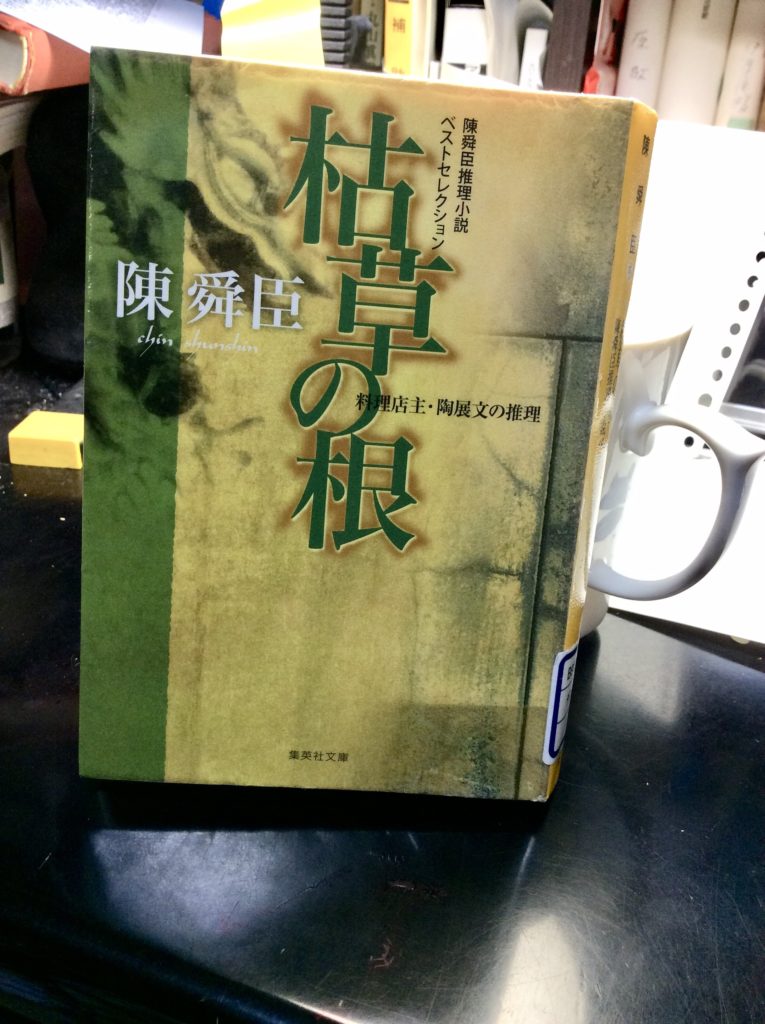
「枯草の根」陳舜臣、1961年発表、講談社
陳舜臣氏の初期の作品はこういうミステリーものだった。しかしすぐに歴史ものや紀行文学に移っていって、このミステリーものは数が少ない。
この本は江戸川乱歩賞受賞作品である。彼の37歳の時の作品である。
“神戸に住む中国人たちのミステリー” の続きを読む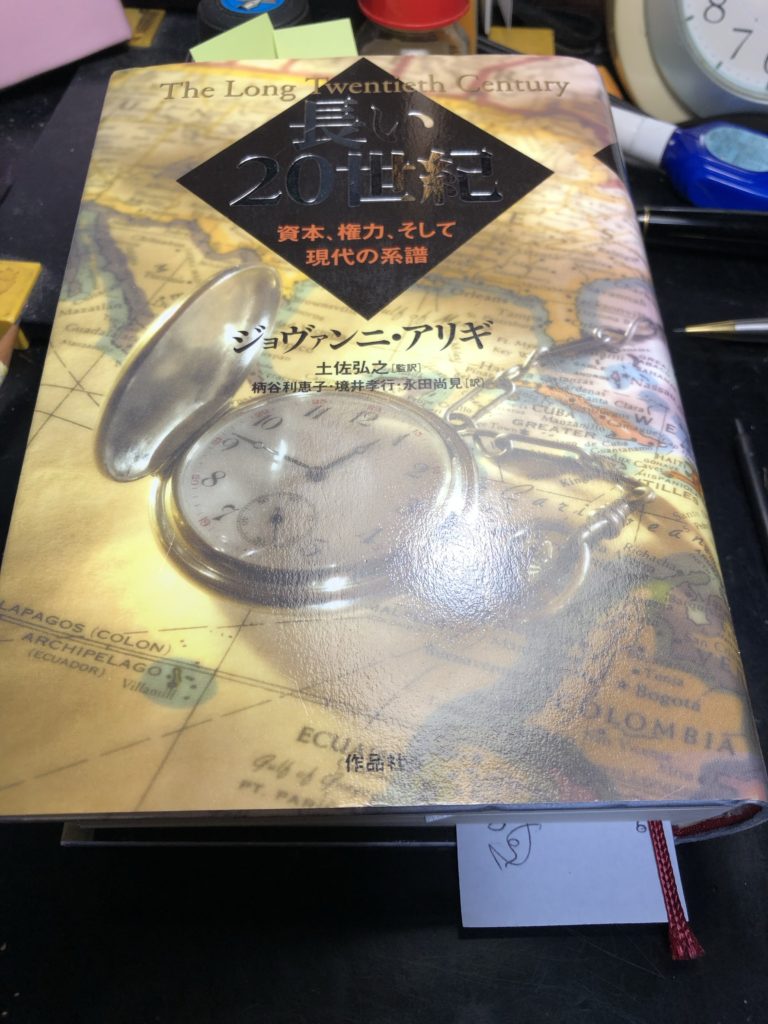
長い20世紀(資本、権力、そして現代の系譜)、ジョバンニ・アリギ著、作品社、2009年発売、原著は1994年発行、(1995年のアメリカ社会学会、世界システム政治経済部門賞受賞)、5200円
この本は約600ページの厚みのある本である。この本を読み始めてから約1か月半である。最初は図書館の本で済ませていたが何回も延長できず、ついにネットオークションで安く買うことを画策して、手に入れた。
“世界の経済覇権はどのように推移したのか?” の続きを読む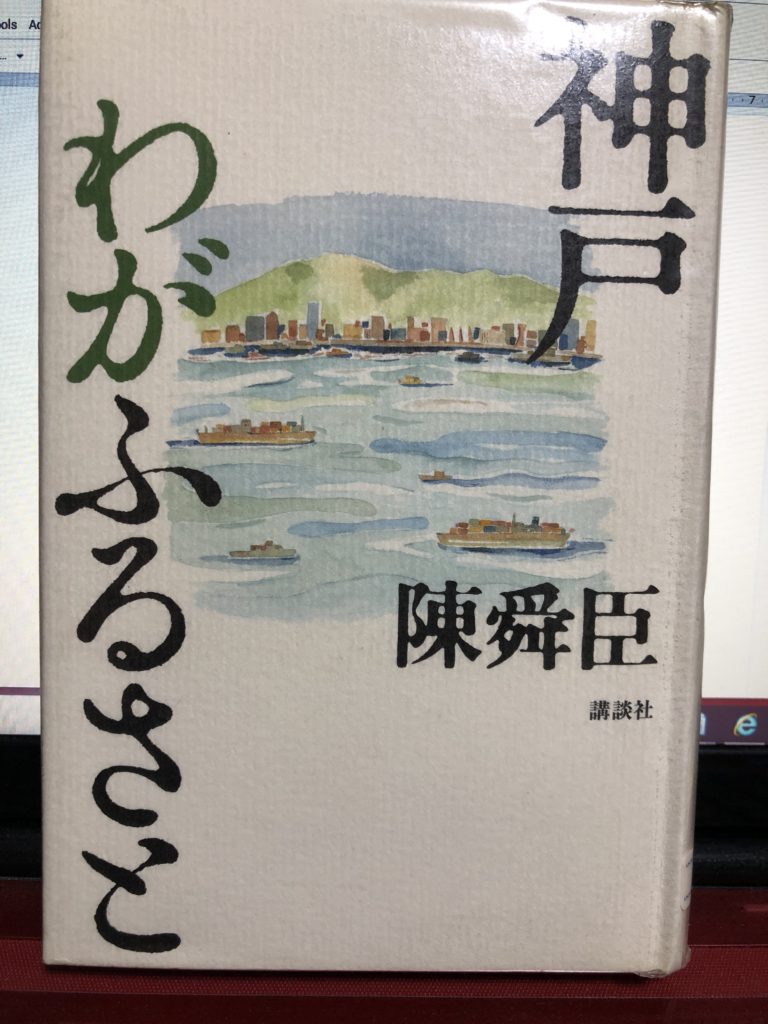
陳舜臣、神戸わがふるさと、講談社、2003年発行
第一部と第三部がエッセイとなり、真ん中が小説となっている構成である。
このエッセイの最初の文章が素晴らしい。なんという悲劇、なんという歴史。
“慟哭の歴史” の続きを読む南海の王国琉球の世紀、東アジアの中の琉球、角川選書、平成5年(1993年)発行
(陳舜臣、森浩一、山折哲雄、濱下武志、高良倉吉、田中優子、井沢元彦)
この本の構成は、まずそれぞれの専門分野の部分を発表し、それをもとに、7人で議論をする。議論の方は2部構成で1、琉球王国の誕生と形成、2東アジアの中の琉球。
なぜこの本を読むのか
“アジア史の中の沖縄、新しい視点から” の続きを読む「北京のアダムスミス」(21世紀の諸系譜)ジョバンニ・アリギ著、作品社、2011年発行、(原著は2007年発行)673ページ(ページがふってある箇所だけで)
この本は、ネグリの大著、「帝国」をさらに上回る厚みである。
この本を読むのにやはり一か月はかかった。長い本である。
“衰退する米国、台頭する中国” の続きを読むアントニオ・ネグリ、マイケル・ハート著「帝国」ーグローバル化とマルチチュードの可能性、水嶋一憲他訳、以分社、2003年発行、約580ページ
(この本を一か月かかって一応読了した。読了したが、この本を読んでわかること分からないこと分かりにくいことなどあって、全部理解できたというつもりはないし、逆にわからなさが重要なのかとも思えてくる。その後、手にした「さらば”近代民主主義”政治概念のポスト近代革命、アントニオ・ネグリ著2008年、作品社、を読んでからのほうがよくわかる仕掛けである。)
空爆下のユーゴスラビアで、-涙の下から問いかける、ペーター・ハントケ 訳元吉瑞枝
同学社2001年6月発行
以前書いたコソボ紛争の中でペーター・ハントケの名前が出ていたのでこの人の本を読んでみたい、と思った。(ブログ;コソボを知るにはこの本を読むしかない)
今回はちょっと硬い本を取り上げる。
改定「社会科学概論」寺尾誠、慶應義塾大学出版会、1989年の初版を97年に改定新版として出版。
この本は、私が大学の時に師と仰いだ、寺尾誠教授の本で、我々が学生の時にはこの種のまとまった本は彼は書いていなかった。5年前に亡くなったのだが、一昨年大学で3周忌といったか追悼の会があった。その時にあとで書いてある,哲学者花崎こう平氏への手紙をまとめた「歴史哲学への誘い」という本をいただく。かなり分厚い本だ。そういうこともあり、一度しっかり寺尾さん(以下寺尾さんとする)の本を読むべきと思ってこの本を手にした。
邱永漢「濁水渓」中公文庫、昭和55年(1980年)(初出、昭和29年、1954年)
この本は直木賞候補になったそうだ。「香港」(昭和30年、1955年直木賞を取る)