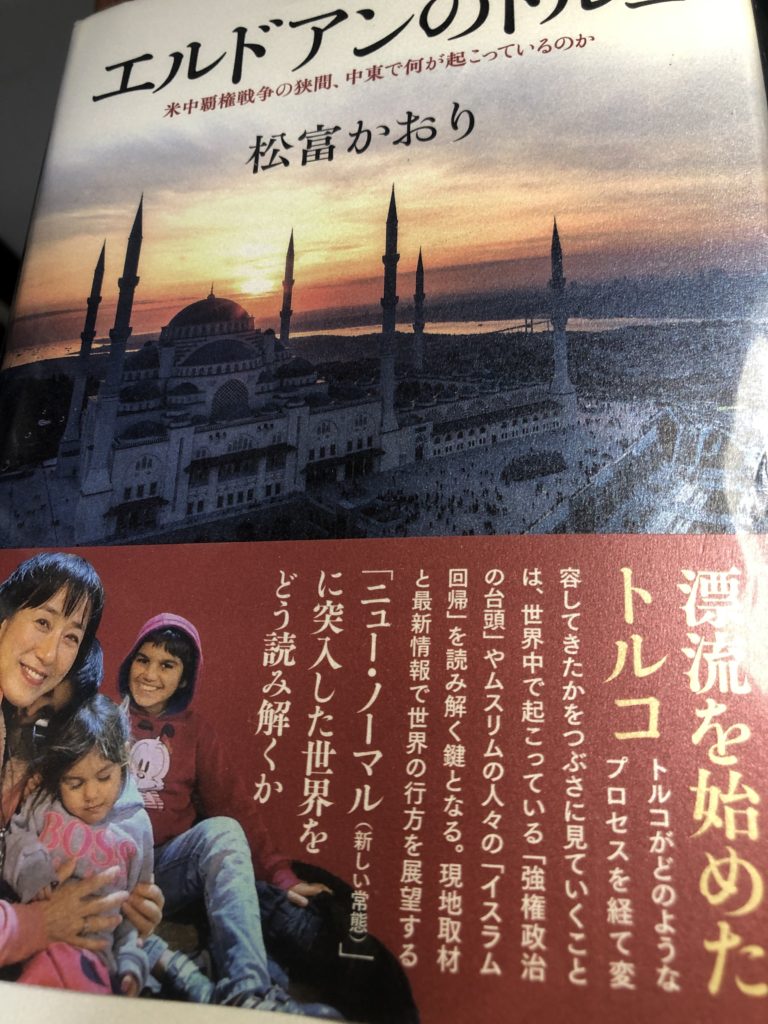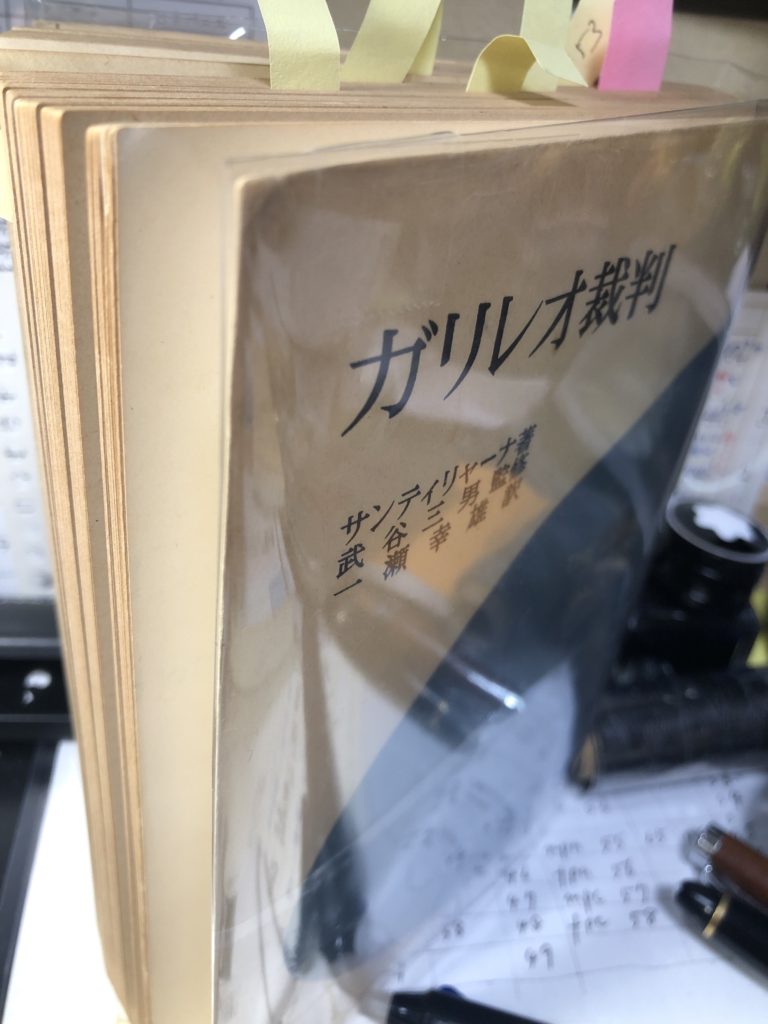エドワード・W・サイード著「パレスチナとは何か」写真ジャン・モア、島弘之訳、岩波現代文庫、2005年発行(原著1995年岩波)
エドワード・w・サイードとは
この本は、パレスチナ出身アメリカで教鞭をとっていた世界でもっとも著名な思想家の一人である、エドワード・サイードの本である。彼のもっとも有名な本は「オリエンタリズム」(上・下、平凡社)である。「オリエンタリズム」は今もなお世界中で蔓延しているヨーロッパ中心主義(欧米という西側)という世界の視点を明確に問題視したのである。マルクスでさえ彼の批判にさらされている。欧米中心史観、欧米中心の世界観というものを徹底的に批判したものである。決してそのヨーロッパの文化遺産を否定したのではなくその視点を批判したのである。