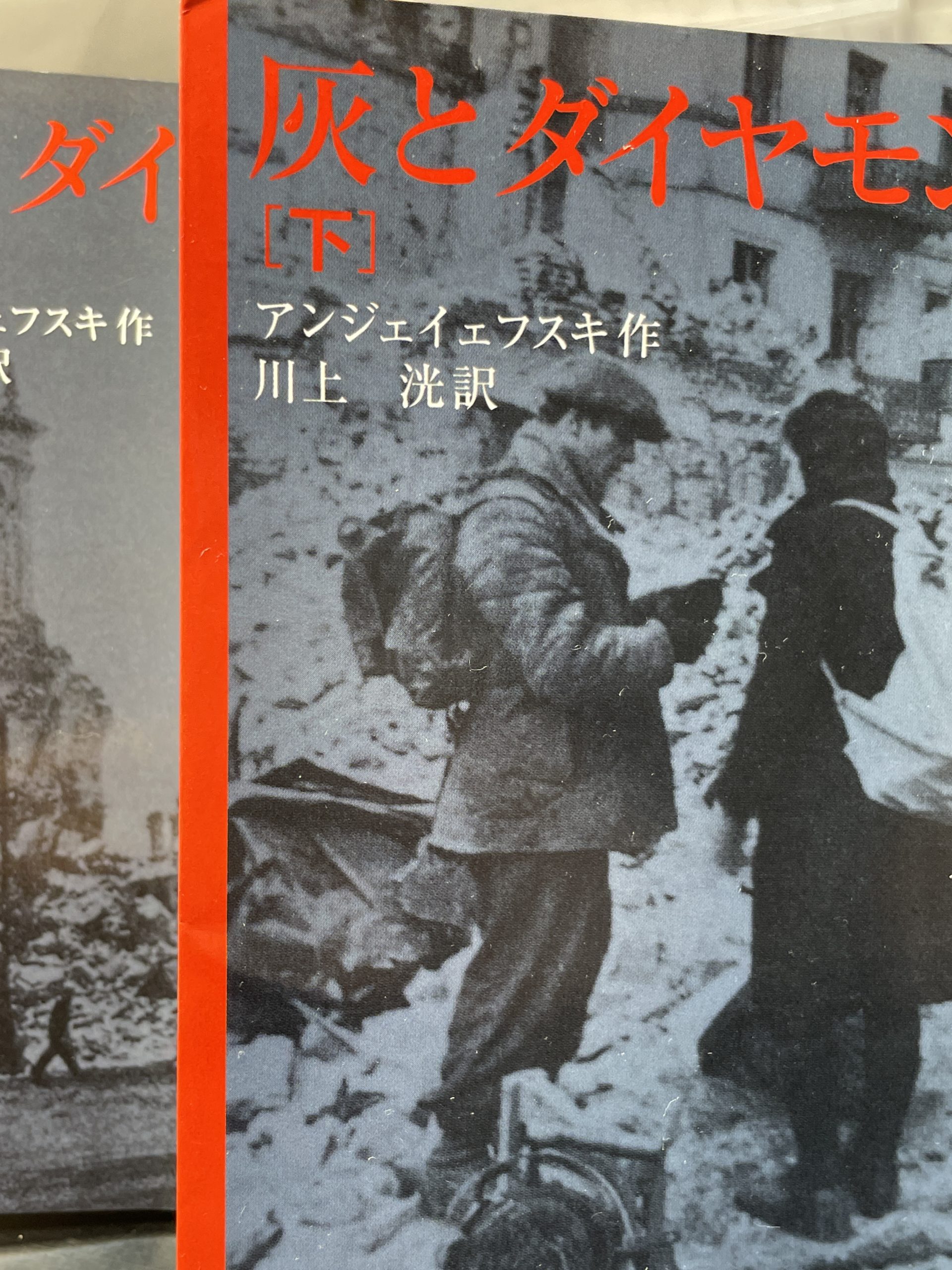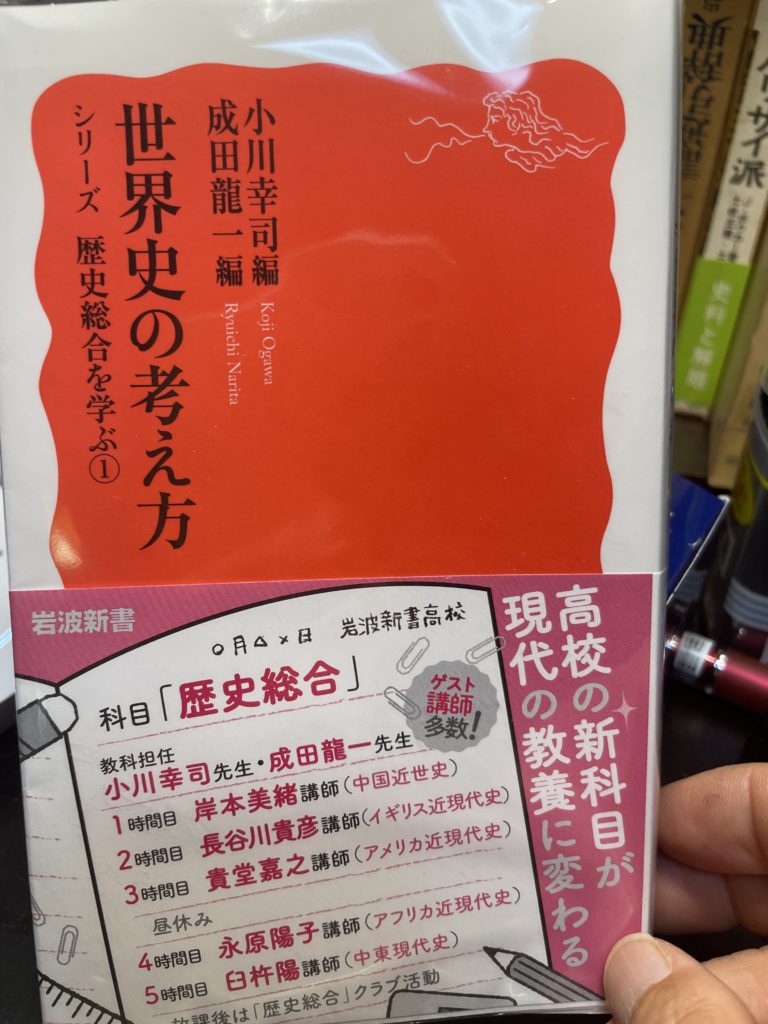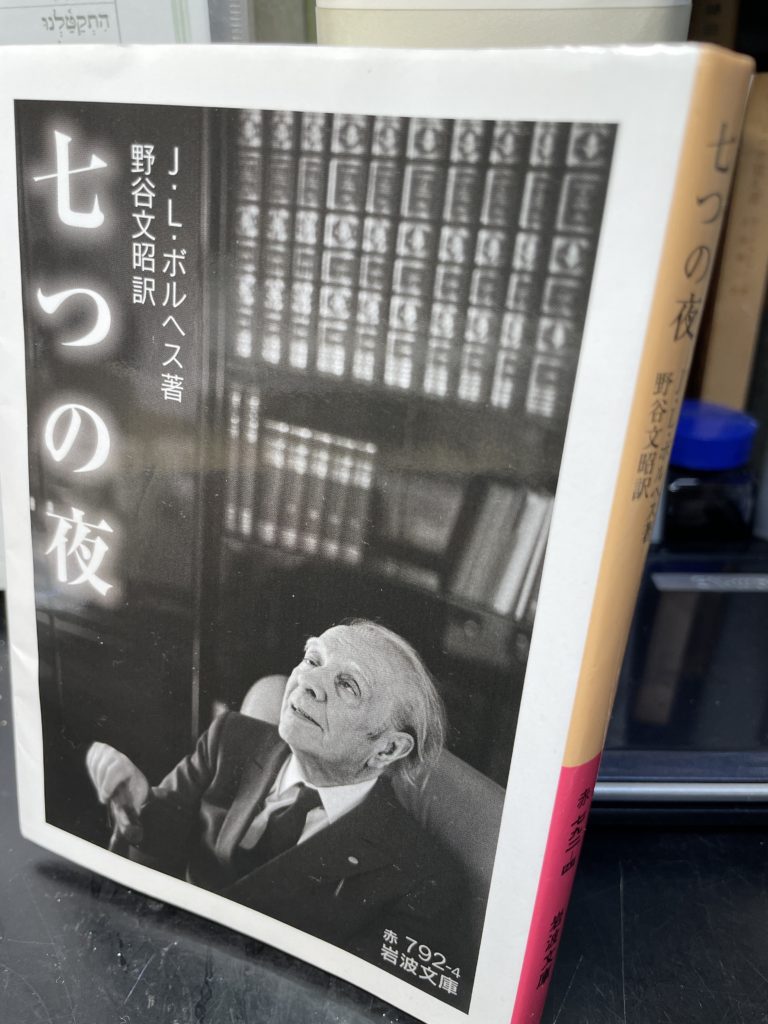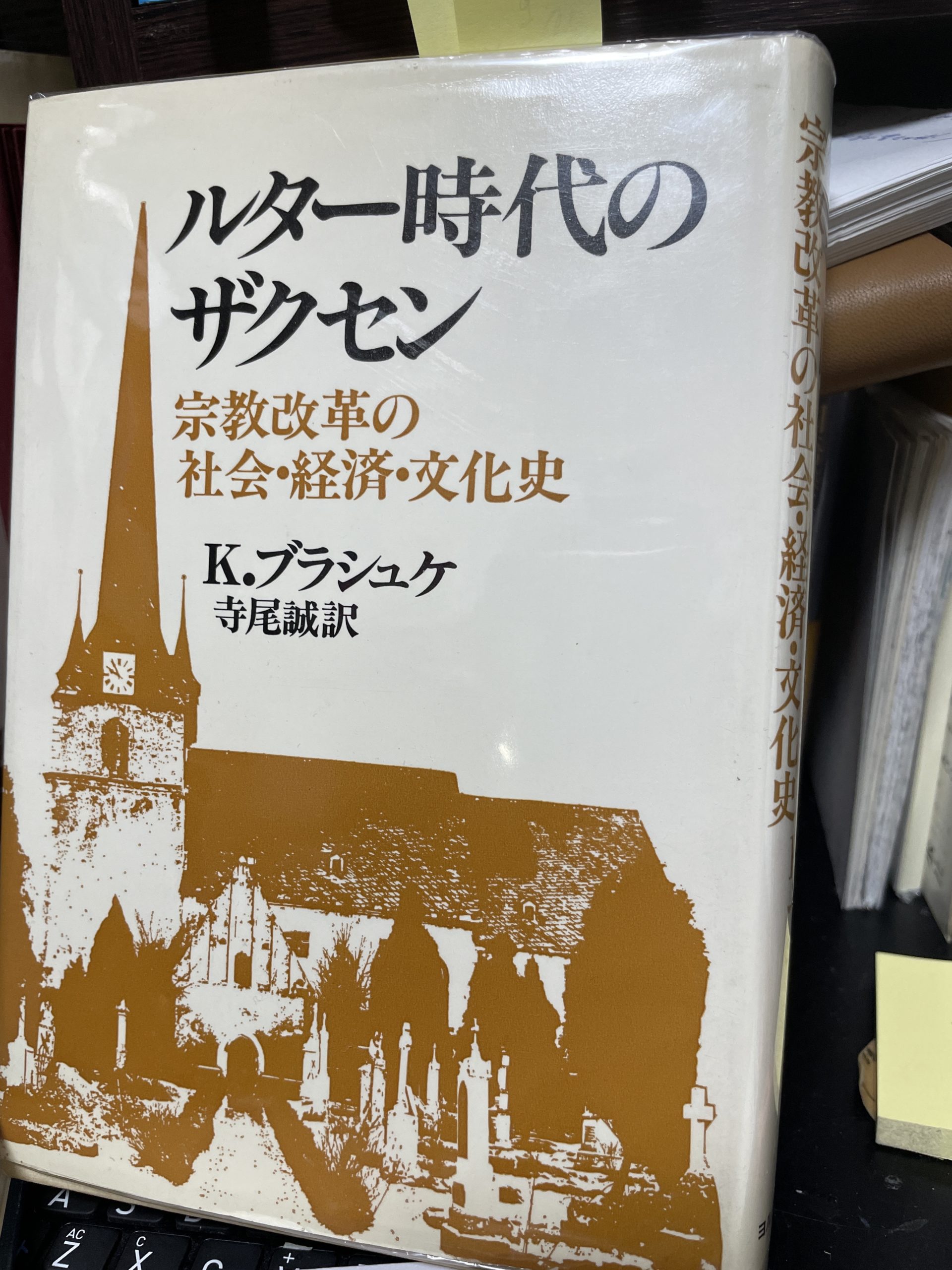「大塩中斎」、宮城公子編集、洗心洞箚記、檄文、1959年発行、日本の名著第27巻、中央公論社
なぜこの本を読むのか
ウクライナの戦争などあり危機の時に学者の評論などたくさん見るにつけ、学者や評論家の本音はどこにあるのかとか、あなたは主体的にこういう時どういう行動を起こしますかというようなことを聞きたくなることがたくさん出てきた。学者や評論家というのはあるテーマだけに絞って出てきていかにも訳知り顔に語るのではあるが、はっきり言ってどうなっていくのかはよくわからないというのが実情だし、
そういう学者や評論家も本当のところはわからないといったほうがいいのだろう。こういう問題が起こった時に知っておくべきことや背景などは学者や評論家の真骨頂となるところである。しかし本質は現実なので、預言者でない限り非常に予測不能であるし、将来を見据えることもできないだろう。学問と現実のせめぎあいの葛藤の中に彼らはいるのか、いないのかなどと考えているとふと、学者だった大塩平八郎がなぜ大阪で大反乱を起こしたかということに非常に興味を覚えることとなった。その彼の陽明学というものに革命的な反乱的な思想が含まれているのか、それともそれとは関係なく指導者としてやむに已まれずの事だったのかとかはっきり言えば彼の動機と彼の学問との関係を知りたくなった。大学の先生で革命を目指す人なんて言うのはほとんどいない。マルクスは学者ではあっても大学の先生ではなかった。大塩も在野の学者だった。しかし公務員として何年か幕府に仕えたのである。それも与力というから今の警察である。基本的には体制側の人である。また陽明学というのも革命の思想ではなく支配体制側の思想であるはずだ。しかし彼特有の何かがあるのかめくら蛇におじず、でこの超むつかしい洗心洞箚記を読み始めた。
“大塩平八郎の乱” の続きを読む