「ルター時代のザクセン」K・ブラシュケ著、翻訳、解説、註、寺尾誠、ヨルダン社、1981
なぜこの本を読むのか
・私にとっては非常に関心の深い分野である。またマックス・ウェーバー以来論争の多い分野である。かつてはむつかしくあまりに専門的で、自分には面白くなくて読めなかった。
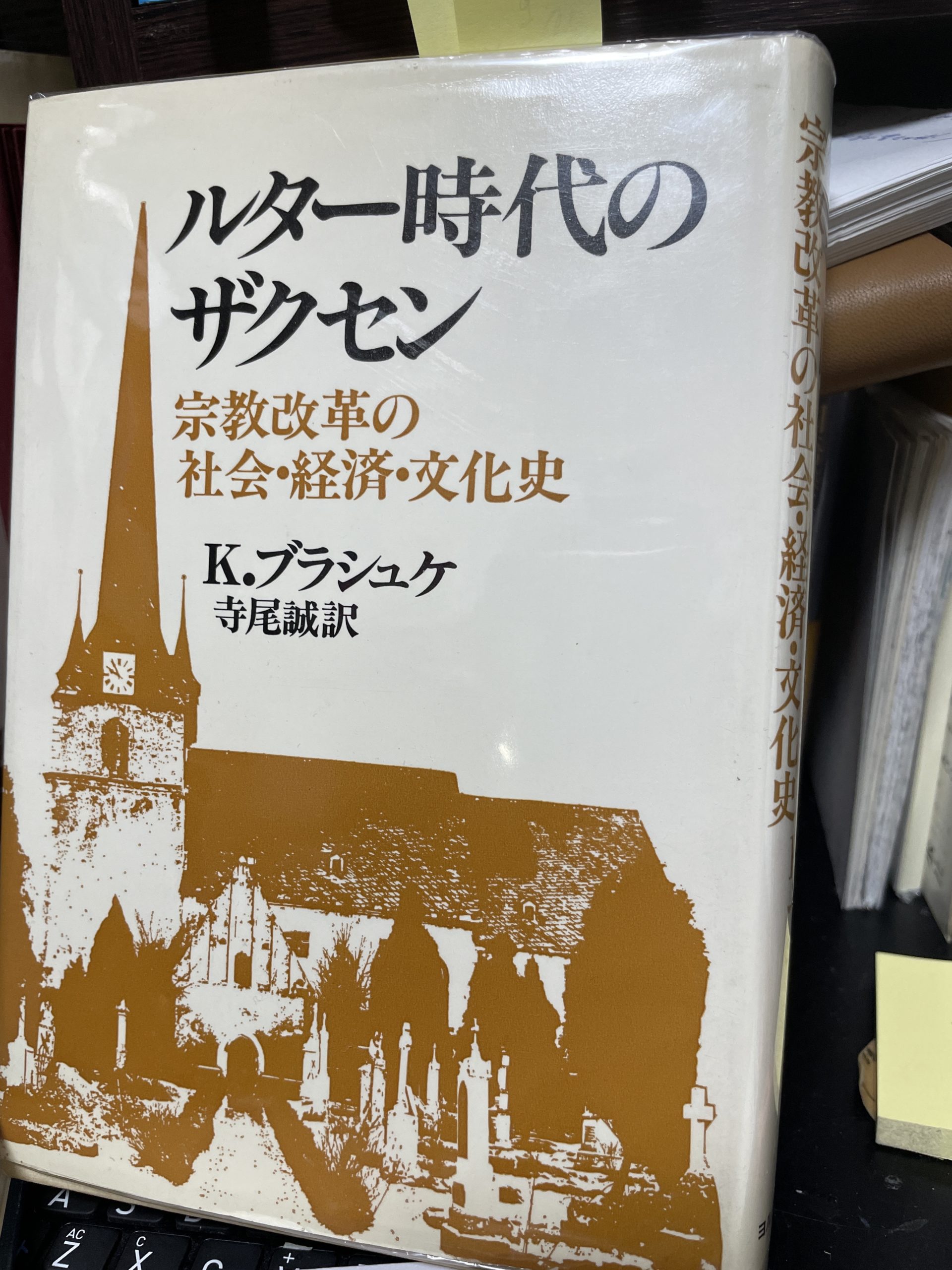
・慶応の寺尾誠さんが翻訳、私の師事した先生であるが、ゼミの卒業論文が書けなくて卒業できそうもなかった時、卒業してから書けと言われて4単位をもらった。やっと卒業した。このことを突然思い出して、冷や汗が出てきた。大学の入学、落第、卒業がいまだにトラウマだ。このトラウマが消えるわけでもないが、勉強しなおさなければと思う。そういう力が寺尾さんにはある。
・この寺尾さんが嬉しそうに、この著者と当時の東ドイツでの交流した時の事ことについて書いてある記事がある。ドイツに行かれた年が1977年とあるから、私はその時はすでに卒業していた。また、あとがきにもあるが、図書館で彼の本を発見した。三田の図書館の書庫とある。その点について彼は「当時、実践の長征と方法への迂回を遂げ、実証の畠へ飛び立とうとして模索していた私にとり、それは幸運の女神の贈り物であった」と書いてある。マルクス主義的実践だっただろうか、マルクスやウェーバーのような理論一辺倒的なところと実証(多様性)とのギャップに悩んでいたのだろうか。このブラシュケは地方史、実証主義的である所に寺尾さんの悩みに光が当てられたのかもしれない。確かにその前に書いている「価値の社会経済史」は理論、方法論である。それはそれで書いた後行き詰まったのか。「遂げた」と書いてあるところからすると行き詰まりではないだろう。理論は多くの事実を捨象する。そのことによる現実の多様性の理解がなくなる可能性もある。またそのことによって現実への厳しい緊張感と理解から離れていくのではないかという危惧だったのか。
また、そこには発行元の友人の当時ヨルダン社の山本さんの事にも触れていて、彼はゼミ8回生とある。また青年老い易く、学成り難し、一寸の光陰軽んずべからず、朱熹(12世紀のはじめ、朱子学創始者)の作、「偶成」と言われている、この詩を著者にドイツ語に翻訳してささげた。(この内容が書かれている記事は寺尾さん3周年記念の時もらったと思う。)
やはり寺尾さんが訳したということが重要である。
この本
この本の翻訳のいきさつ、彼との出会い、交友関係については、あとがきに詳しい。
彼の本はほとんどそうだが、あとがきが長くておもしろい。自分の言いたいことを存分に言っている。このあとがきは、ブラシュケという著者が当時の東ドイツにいたということもあり、彼の社会主義論、彼のキリスト教論、社会経済史の方法論、彼の思想的立場というものを感動的な筆致で紹介している。こんなに感情的な寺尾さんを見たことがないというくらいの内容である。書ききれない感情があふれ出している。熱いものがある。経済的にも貧しい東ドイツの小さな家での深く温かい真の交流がここにはあったのだ。ここだけ見ても寺尾さんという人は大変な学者であり、思想家であり文筆家であり、情熱家であることを感じる。(彼はパッション情熱とシュパヌンク緊張が必要だ、と口癖のように語っていた。)本当は泣いて書いたのかと思わせられる。泣く人ではないが。この内容については知りたい方はぜひ本を取って読んでほしい。「神の総体」という言葉に感じるものがあるだろう。
内容
「ルター時代」というのは1500年から1555年くらいまでのドイツのザクセン地方の歴史である。歴史的にみると非常に短い期間を扱う上にザクセンという一地方を扱っておりある意味の地方史である。社会経済史であり、専門家の本というよりは、一般向けの本ではあるがそれでもいったい誰が読むのかと考えれば、ルターという宗教改革者のいた時代とその生み出されてきた環境というものを知りたいと願うある種の専門家ではないだろうか。ましてや今読む人はほとんどいないだろう。今から40年前の本である。増刷を重ねているという話も聞かない。しかし隠れた逸品というしかないだろう。その解説も含めて。
内容についていえば、彼は古文書、教会などにある、を事細かに調べてその史実だけを頼りにザクセン史を書いたという。当時の都市別人口や農民の比率、さらに収入もある程度わかるようである。この詳細なデータというものがいまだに残っているということがものすごいことではあるが、イギリスのサスペンスなど見ると過去を調べるには教会に行けということがよく言われている。教会には多くの古文書が残っているようだ。現在は古文書館というところで一括して管理しているようだ。
彼の狙いはどういうところにあるのか
つまりルターが出現して、1517年秋ヴィッテンベルグ城の門に95か条のラテン語で書かれた定義条文から発したヨーロッパ全土を巻き込んだ宗教改革というものがルターという個人の天才の力があったのでこのように大きな変化を呼び起こしたのか?それは本当か?という問題意識が一つある。スターリニズムはスターリンだけの問題だったのかという、あるいはナチズムはヒットラーの狂気がそうさせたということなのか、また現在のプーチンの思想が今回のウクライナ、クリミヤ危機を招いているのかというような事にも通じてくるある意味では現代的、現在的テーマでもある。社会経済史的にみると一個人の力だけとは言えない。彼じゃなくても誰かがやったということではないが、ザクセンという地方の持っている歴史的な特性がここまでの大きなプロジェクトにしたのだということではないか。これは歴史の解釈でもあり、史実の見方でもあり、常に問題にされるところでもある。彼は歴史の総体という言葉でこの個別史を見ていく。理論がないのではない、理論を奥深くしまっておいて史実の多様性に語らせるということなのである。もう一つは彼の認識の方法である、史実に語らせるという方法であるが、これが歴史とは何か、という理論的思想が奥に潜んでいる。(これについては寺尾さんが甘いとか批判をしている。あとがき参照)
ザクセンというのは鉱山業の発達した地域で彼は初期資本主義という言葉を使っている。鉄その他の金属などが採掘されている。それによって、高炉まで作られたようだ。この原料から金属加工という技術がのちのグーテンベルグまでつながる。このあたりから資本主義的思想というものが芽生えてきたということなのかもしれない。また城壁の中では市民が急成長を遂げ現物経済から貨幣流通の世界への変化を一番享受した。また農民戦争に見られる通り、貴族などの騎士的甲冑で身を固めた戦闘要員はもはやいらなくなった時代に入っている。そこでむしろ領域の統治的手腕が必要な時代になっていた。裁判の必要性からローマ法の導入や市民的教養の育成、記録文書の作成、計算業務、報告、命令業務などの必要から大学教育というものが要請されていた。さらにグーテンベルグが活版印刷を発明した。ただし、彼はルターの一時代前の人である。(1399年から1486年)ほとんど重なっていないが印刷技術の発展がこの新しい時代の要請にこたえたのである。またルターの95か条についてはラテン語で書かれたのだがあっという間に翻訳されドイツ語で2000部ほどすぐ売れたという。こういう事実から考えるに広範囲に読み書きができる人たちがいてこの種の印刷本を買い求めたのである。
ザクセン南東にあるボヘミヤにはフスの宗教改革があり、この影響も受けたトマス・ミュンツアー(ルターの影響を受けた神学者、牧師、農民戦争指導者、革命的思想の持主、ルターと同時代)が農民とともに農民戦争を起こした。チェコの神学者フルマートカは初期宗教革命といっている。(佐藤優の崇拝している方だ。)こういうことがあってのルターの存在であった。土地制度史、キリスト教会史、教育史、芸術史、建築史、農業技術史、鉱山技術史、文化史を駆使して叙述している。
彼の本の全体をまとめることはできないが、大体以上のような内容である。
終わりに
寺尾さんは今はもういないが彼の思想は残っている。古いとか新しいとかいう問題ではない。生き生きと生きて残っている。私自身会社に入った翌年、冬のボーナスを全部使ってけちけち旅行友の会に入り飛行場で往復切符をもらいドイツへ行ったことを思い出した。エルベ川を見たかった。またハンブルグやリューベックなどの商業都市を見たいとの気持ちに駆られてであった。冬の一週間であったか、10日あったか忘れた。初めての飛行機だった。
自分自身もそうだが、決着のつけられない問題が残っている。ウクライナ危機の問題も根が深い。ギリシャ正教の問題にもさかのぼる。今なお戦争をするのである。あのニューヨークを襲ったテロのような戦争が。人間の罪深い考え方は変わらないのか。2022年2月、戦争反対を胸に抱き、ロシアのウクライナへの侵攻、侵略をテレビで見、恐れおののきながら戦況を見守り、世界の動きを注視しつつ、深いところで関係する歴史的問題について書いた。この本を読める人はぜひ読んでほしい。
