フィラウィス・ヨセフス「自伝」秦剛平訳、山本書店、1978年
(前書き山本書店主、解説、あとがき秦剛平)
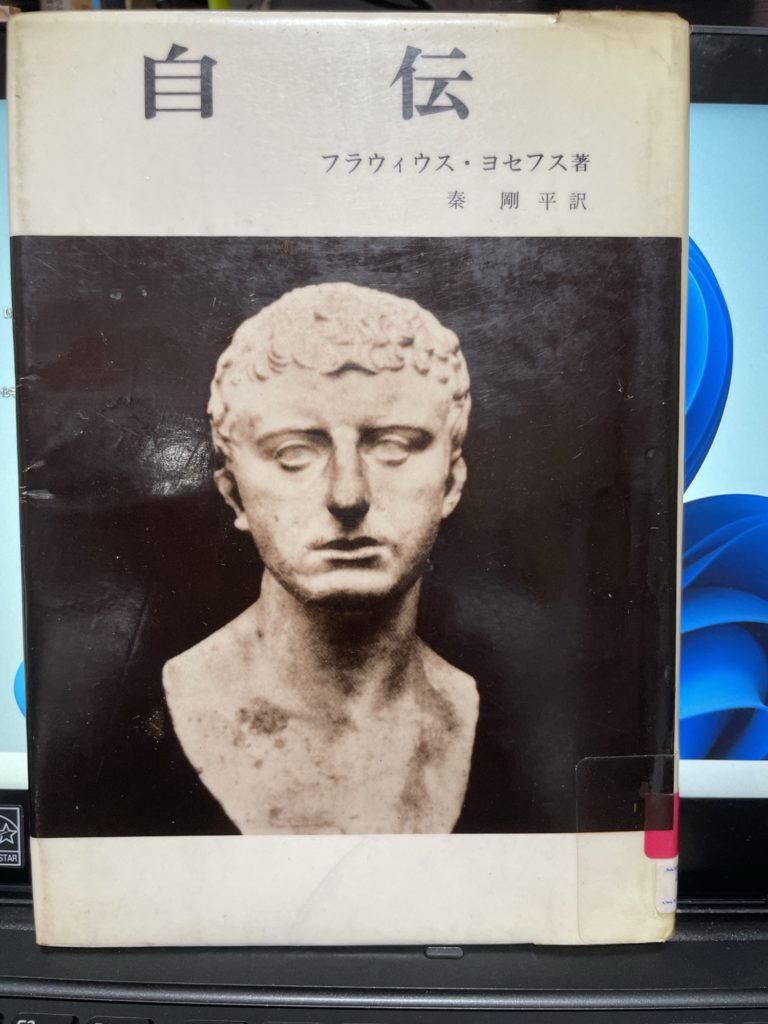
なぜこの本を今読むのか
イスラエル問題の現在、いつ終わるとも知れないガザの苦難、ハマスも悪い、イスラエルはもっと悪い、特にネタニヤフ政権はもっとひどい。(オランダハーグの国際司法裁判所はプーチンとネタニヤフに犯罪者として裁定を下した)ことに、今年のアメリカの大統領選挙、インド、ロシア、6/3にはメキシコ女性大統領が誕生するというニュースがあった。そういう世界で選挙の年と言われており、その選挙結果によりウクライナやイスラエル。ガザ問題の世界での扱いが大きく変わる可能性がある。私は、戦争というものの悲惨さ、過酷さ、フェイクな情報戦、、協力する陣営の対立、弾薬工場の増産活動(背後にある産業間の戦争でもある)戦時体制、制裁回避、国内政治の動向による政治家や政策の不安定さ、i1枚岩ではないヨーロッパ、NATOの動向などTVニュースや新聞で毎日読んでいる。やはり強いやつが強いだけだ、との感は否めず。国連決議も弱く実際の行動までにはいかない。グテーレス議長が何を言っても事態は変わらない。
そういうことから特にイスラエルというのはどういう国かということを、このヨセフスの自伝から読み解けないだろうか。あるいはユダヤの戦争とはその当時としてはどんな特徴を持っていて、それが今現在とどういうつながりがあるのか、そういうことを知りたいと思った。
ヨセフスという人物
ヨセフスは自身はユダヤ人でAD37年から100年位まで生きた人である。彼はユダヤの祭司であり、軍人であり、歴史家であり、政治家、ユダヤ王朝の血筋もあるといわれている人物だ。66年に勃発したユダヤ戦争で敗北後、投降。。ローマの軍人に認められ、ローマ皇帝の庇護のもとローマで三代の皇帝に仕え、ユダヤ古代誌、ユダヤ戦記などを書いている。(現在彼の書いたものは4冊残されている。)どちらも結構長いので、この非常に短い自伝のほうを選んだ。長いほうは後ほど読むにしてもこの自伝で概略分からないかな、との思いだ。
この本の時代
この本は本人は29歳前後、時期は紀元1世紀60年代の話である。ユダヤが完全にローマの支配下に組み込まれる紀元前後にローマの属州となりローマ支配下にはいる。その後はローマとの大戦争が少なくとも3回あり、最後の2世紀前半のボク・コホバの戦いをもってユダヤ人は離散の民(ディアスポラ)となる。歴史を振り返ると、少数民族というのは本来はこうやって消えていく運命にあった。たくさんの民族が消えていった。しかしユダヤ人だけは第二次世界大戦後に国を再建した。2千年の長い歴史を超えて国を作った。これがよかったのか悪かったのか。
内容
この本の書かれた目的というものがあって、いわゆる自伝とはあるが、大部の先述した本では書いていない部分を自分を主役として、書いた。そういう意味では自伝であるが、自分の最後の老いさらばえるところまで書いてあるわけでもなく、自分から見たユダヤ戦争記のある部分を切り取ったという感じか。
この本の書かれた目的は、2つある
1,ローマに対してはユダヤ人が、蜂起するのを抑えようとしたが、うまくはいかなかった。しかし自分には反ローマ闘争に加担する気はなかった。
2,一方でユダヤ人に対しては、ユダヤ人の気持ちも汲んでローマとは戦った。己のユダヤ人として覚悟もあって民衆が支持するのでその意思を受けて戦った。ユダヤ人としての本懐は遂げた。
なぜこの2つであるといえるのか。それはユストスというユダヤ人が書いた「歴史」という本でヨセフスの事を徹底的に批判しているということらしい。(9世紀ころまではあったようだが、現在は消失して原本は不明)内容はヨセフスというのは裏切り者で盗人であるというような内容らしいが詳しいことはわからない。だからユダヤ人として裏切りについての反論、とローマとの戦争についての責任について書かざるを得なかったのではないか。そういう意味でこの本は戦争責任に対するローマ支配層への自己弁護であった、と言われている。またそういうことをしっかりと反論できないといついかなる時に失脚させられるかわからないという彼の地位の不安定さもあっただろう。
詳細は
ヨセフス(当時29歳)がユダヤ人祭司の救済のためにローマに何か月間か行って,その案件を彼の人一倍の頭脳と知恵で解決して帰ってきた時に、反ローマ闘争の機運が一気に高まっていたという。
反ローマ闘争の主因は、ローマに支配されているということからくる。発端はカイサリヤ(イスラエル北西の海岸沿い、ローマ軍の駐留基地があった。)におけるユダヤ人殺害である。これをきっかけに過激派の暴動がおこった。(ウイキペディアによる)
現在でもあるガリラヤ湖周辺のガリラヤ地方が主なる舞台である。ここは対ローマ戦では非常に重要な戦略地点となる。場所はエルサレム北方の要所、でローマ軍がここから攻めてくるようなところであり、ここが陥落すればエルサレムまでは一直線に攻め込まれてしまう場所だ。ここでガリラヤ人(聖書では異邦人のガリラヤ、と出てくる。)がユダヤ人とともにローマ軍と戦おうとする民衆の血気盛んな動きの中で、彼はそれを鎮静化したり、あるいは諜報活動をして過激派を抑えたり、自分の敵になりそうな人物を言葉巧みに民衆から離反させたりと手練手管を散々使って難局を乗り越えていく。しかしユダヤ人の反ローマ闘争は次第に熱を帯び、ローマ軍もガリラヤ近辺に進軍してくる中で、ユダヤ民衆によって担ぎ上げられて、仕方なく指揮官として最後は戦うことになる。そこで話は終了している。非常な短期間の話である。
補足
この反ローマ闘争というものの補足をするとすれば、塩野七生著「ローマ人の物語」(7巻)に詳しいが、エルサレム神殿にローマの皇帝の像を置く、とか安息日を守ることができないとか、ローマ皇帝を拝せよとかそういう一神教のユダヤ教の戒律の譲れない部分での問題が起きたり、エルサレム神殿を破壊するとかすると一気に熱を帯びてくる。しかしその塩野氏の説によれば相当にローマは寛容だったということだ。ユダヤ人の特性をよく理解しその民族の文化を尊重するような支配構造だったという。非寛容であったのはユダヤ人の側だ。彼女はそう分析している。当時アレキサンドリアには20万人、ローマには8万人のユダヤ人が暮らしていたというから、文化的融合は相当な勢いで進んでいたし相互理解というものはある程度あったはずなので、ローマ側ではユダヤ人=奇異な民族という認識はなかったはず。問題が起これば融和的政策もしている。かつローマも支配統治できればいいのであるから、必ずしもいつもいつも強権発動はしたくないという。そうなのであるが、カッカしていたのはユダヤ人である。安息日は守っているにしてもモーセの十戒の殺すなかれ、は守られたことがない。M・ウエーバーの言う体内倫理ということか。イエスもこういうことに関しては厳しい批判をしている。
続きは
この話の続きは解説によると、ローマ軍に打ち破られて徹底的にエルサレムまで焼き討ちにあった。その後何十日かのヨセフスは籠城(ヨタパテの籠城、として有名)をして最後に降参で出てきた時、敵将のウエスパヌシウスにとらえられる。しかしそこでヨセフスが敵将にあなたは将来皇帝になると言い放った事が予言ではないかと思われて彼自身は助けられその後の人生もローマで3代の皇帝に仕え、通訳兼仲介者として活躍した。
この物語の特徴、大衆
現代でも通じることだが、無政府状態だったユダヤという国が反ローマ闘争を戦うということからかもしれないが、大衆の役割が非常に大きい。アゴラ=広場で指揮官たちあるいは支配層は必ず演説する。そうするとその話を民衆・大衆は納得すると収まり納得しないと猛反発して指揮官さえも引きずり落とすということになる。結構細かい内容について大衆的関心のある事柄はそういう演説テーマになる。これはイエスが十字架にかかる時に大衆が示した行動とさほど違わない。十字架につけよ、という大騒ぎになって仕方なく承認したことになっている。イエスの生きた時代とこのヨセフスの生きた時代は30年くらいずれているがそう変わらない。
ゼロータイ
実際反ローマの思想はイエスの時代からあって、パリサイびとがイエスを追い落とそうとして、質問する。ローマへの税金はしたほうがいいのか悪いのか、これに対して、イエスは答える。カエサルのものはカエサルに神のものは神に、という。この答えでパリサイびとはグーの音も出なかった。またユダヤ人はゼロ―タイ(熱心党と訳されている過激派)という一派がいた。イエスの弟子にもこの熱心党(ゼロータイ)がいた。同様にキリスト教の世界的広がりに力のあったパウロもこのゼロ―タイにいたといわれている。パウロはゼロ―タイの裏切り者であった可能性があるという。そのためにユダヤ人から付け狙われていた。(トロクメ、キリスト教の幼年期、ちくま学芸文庫)昔から過激的、暴力的解決を狙う集団が活発化していた。
結論として
このユダヤの戦争もまた、大衆政治に左右されていた。この自伝では、大衆政治的なことは解説などでは全く指摘されてもいないが、現在の我々の目で見るとそういうことが暗黙裡に語られている、ことがわかる。やはりなんといってもこの大衆の問題が政治的には非常に重要なのである。どのように大衆が動くかで政策は決まってくる。今もなお、トランプやバイデンなどの両陣営も大衆の離反を防ごうと自分の考えも捨てて妥協的なことすら言い出す。バイデンはイスラエルの戦争を止める気もないわりに若い人のバイデン離れを防ごうと、思ってもいない政策を打ち出す。逆にプーチンの支配するロシアでは大衆が自分に不都合なほうへ動こうとすると強権発動なのである。ローマ的法治主義レベルの余裕はない。そのことだけについていえば古代ローマより劣っているのかもしれない。ネタニヤフもある程度の大衆の支持があってあの虐殺行為をやっているのである。
現在の大国の政策、あるいは日本の政策も同様でこの「大衆」の動向がやはり重要なカギを握っている。そこが現代と相通じるし、ガザの問題の淵源でもある。またユダヤの過激主義というのは今に始まったことではなく長い歴史のあることだった。
