渡辺泉著、会計学の誕生ー複式簿記が変えた世界、岩波新書2017年11月発行
この本をなぜ読むことになったか。
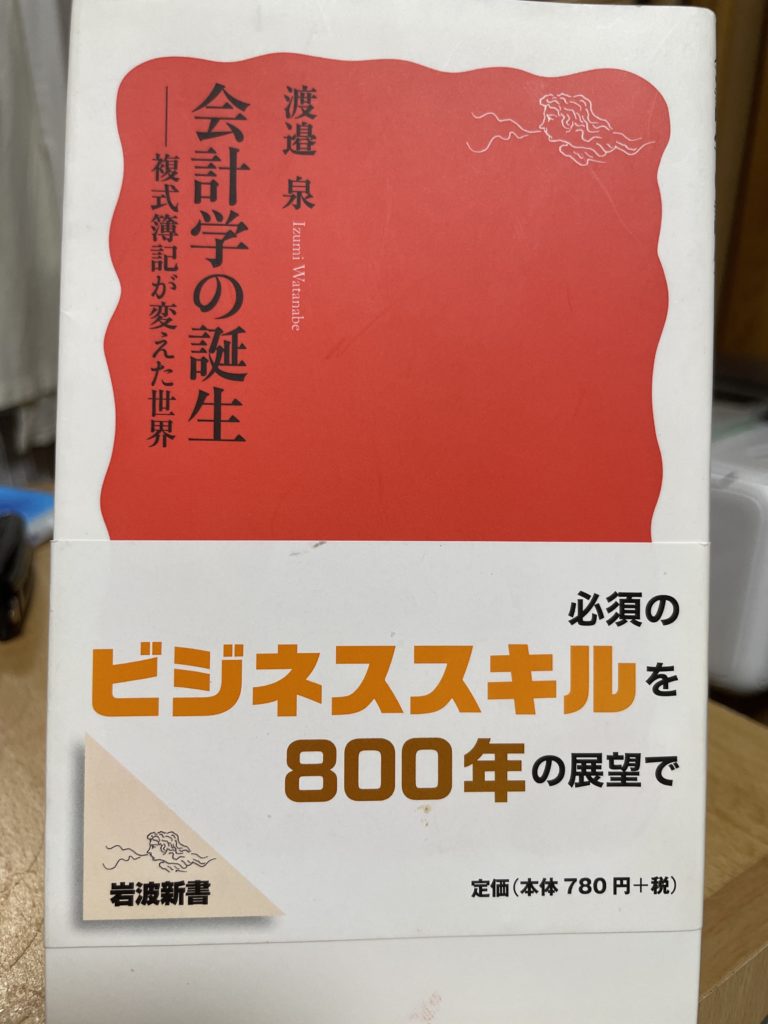
1、複式簿記は,M.ウェーバー、マルクスなどが近代資本主義の重要な発明でかつ資本主義に固有であると言っていた。
2,仕事をしていた時には経理の仕事は私には全く関係ないと思っていた。会計はわからないことが多かった。特にここで表題に出ている複式簿記の本来的な意義というものがよくわからなかった。
3、その後決算とか、経常利益とかそういうものに関係して自分で発表しなければならないことも出てきたが、それでも充分分かっていない面もあり気持ち悪かった。
そんなことから今しかこういうことをしっかり勉強できることもないだろうと思い、それも歴史から振り返れば少しはわかってくるだろうと、考えた。かつ岩波新書でそう厚くもないし読みやすそうだ。
そうはいってもなかなか複式簿記の重要なところが見えてこないので、簿記3級入門という本も脇に置きながら読んでみた。
この本の流れ(大幅に省略して)
会計学の誕生がテーマなので、複式簿記の発生だけで現代の会計学ができたとは言えないということになっており、そこから会計学への一歩が長かった。この複式簿記から損益計算へができるところまで行かないと現代の会計学へ近づいてこない。現代会計学はこの複式簿記、損益計算書、貸借対照表がセットになる必要がある。さらに現代では、特にキャッシュフローが必要になった。これはなぜか。資産と損益計算では利益が出ていたとしても、その利益たる現金は実際どこにあるのかということが問題となった。19世紀のある大手の鉄鋼会社が利益が出ているので次の投資をしようとした時に、手元に現金がなかった。なぜということになりその当時の工場長が計算を徹底的にやり直してみたら、現金は在庫の中にあったという訳です。たしかに在庫も評価額で計算しますから、利益になっておかしくはない。また、株主、投資家、投機家また利害関係者への主体である当該企業の説明責任については、現在では当該企業の将来はどうなるかという展望まで示す必要があるという議論が出ている。著者は、会計学は事実だけの学なので未来のことについてはかけない、といっている。
発生起源は13,14世紀のベネチアから複式簿記的なものが出てきたが、基本的には18世紀から19世紀のイギリスにおいて現代の形ができたそうだ。長い時間がかかった。
この本の要点
歴史を知ってどうなる、という人には、この本は最後のほうを読めば現在時点での会計書類の意義と動向を知ることになるだろう。このあたりを読めば株主総会に行っても質問くらいはできるかもしれない。
複式簿記とは何か
(簿記3級レベルで基本的なことを覚える。取得された方はよく知っていると思う。)
私はこの簿記というものを全く知らないで生きてきた。しかし今勉強してみるとそんなに難しいものではない。資格を取る取らないは別の問題として理解できるかどうかはそんなに難しくないのではないか。実際にノートに問題を解いて書いてみるといやにわかりやすいと思うかもしれない。しかしこの簿記の原理を知らないと、上に書いた会計3点セットあるいは4点セットが本当にわかったとは言えないのである。だからこの簡単な簿記さへ入門できれば案外簡単な話である。
借方、貸方
借方、貸方にほぼ意味はなく、左のほうに資産の増えたものを書く、右にその時の資産の減少したものを書く。複式簿記とはこれを理解するだけだ。左の借り方はの意味はと考える必要はない。これを考えるとややこしい。
借り方 貸方
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
車 200万円 現金 200万円
と書くのが複式簿記なのである。複式とは借方、貸方の両面にこのストックの増減についての記事を記載するのである。これはフローも意味しており、車を買って会社には一台の車が置いてある。これを運送用に使いたい。一方でそのお金は200万円かかりました。自分の持っていた金庫にあった資本金からは200万円減りました、というような解説が可能なこの一行なのである。最後にたとへばこうして一か月過ぎて色々書いて全てが書き終えた時に、両辺の足し算が一致しているということになる。当然といえば当然だが。基本的にはこれだけのことである。(これだけのことであると言い切っていいいかは分からないが今の私にはそう思えてくる。)
簿記3級の3分の1くらいまで読んでそこにある20題くらいの例題を解けば大体のことは分かるようになってくる。しかしその程度では経理は任せられないということにはなるが、貸借対照表、損益計算書などを読んで理解できれば専門家でない限りそれで済ませることもできる。
というよりここでの教訓であるが、簿記3級とは案外易しい。理解しやすい。もっと以前に勉強していればと地団太踏む次第である。(私自身、3級と1級ではどちらが難しいのかも分からなかった。)
