日本の近代とは何であったか、岩波新書、三谷太一郎2017年3月発行
大体、1870から2000年位までの日本の近代の歴史を大きくとらえ現在までの発展に何が基本的に重要だったか、どういう問題を残したか、今後どういうことが必要かというような内容である。

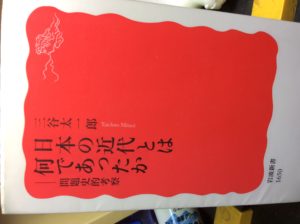
近代という問題は、多くの人が使う言葉であって何をそれで言っているのかは近代という言葉だけでは分からない。古くは米国の駐日大使のライシャワーの「近代日本」というのがある。
これは第二次大戦後の目覚ましい日本の復興を基準に書いたものだから成功する近代日本という意識で書かれている。成功した近代化という言葉で表現している。現在ではこういう見方をする人は少なくなってきている。
むしろ急ぎすぎた近代化、圧縮した近代化ということで問題がたくさん残ったというのが現在の議論でもある。最近では戦前は終わっていないのである、という議論がたくさん出ている現状です。戦争下の政治、経済体制が今なおそっくり官僚機構に残っている、という議論が多い。
細かいことはさておいて、この本の一番重要なことは何か。これは第4章に書かれている、日本の近代にとって天皇制とは何であったか、1節、日本の近代を貫く機能主義的思考様式、ここが一番重要ではないかと思うし著者の論点の一番はっきりしているところだ。
1、教育勅語の本質=近代国家の精神的統合
教育勅語の成立過程を述べながら、日本の近代の最大の問題点をここで摘出している。
明治以来、日本が国民に求めてきたことが機能的人間、使用価値のある人間であった。
明治政府が岩倉使節団として米欧を視察に行き、近代日本を作るための米欧先進国の状態を学んだ。この時に彼らが感じた一つ一つが明治政府によって形成されてきた。1、法的整備=立憲制、2、不平等条約の撤廃、3、殖産興業、4富国強兵などなど。
その中でも最大の問題は近代国民国家としての精神的統合である。幕藩体制から国民国家への移行を素早く完成する必要があった。欧米のキリスト教が国民的統合に役立っているという認識から日本には天皇がこの機能を担える、という判断をした。要するにヨーロッパ化を最速に仕上げるのにはヨーロッパにあるものを機能としてとらえ、簡単に移植できるものはその機能を移植しようということである。この時にヨーロッパでのキリスト教の機能に類似するものは天皇しかなかった。それまでは習俗といえるものでもあったが、宗教性もあり国民統合の象徴ともなる、ということで、この機能を天皇制として使うことにした。その結果出てきたのが伊藤博文、井上、、その他側近グループの作った教育勅語であった。しかしその当時の米欧のキリスト教が国家の統合や民衆の秩序意識に役立っていたかは相当問題があって、キリスト教の間でも多くの闘争があり、国の内部でも宗教的な戦争もある。また政治的には貴族の崩壊とブルジョワジーの台頭により階級的問題も起こっている。ヨーロッパへの理解が非常に単純化された理解であり、この機能的な理解と認識にも問題があった。キリスト教の場合は人間の自由な自発性が基本であり、教育勅語は強制なのである。この全く逆のことを同等的機能としてとらえた。実質ではなく形式的機能であった。自由な人格の人間形成ということは追及されず、圧縮した近代を突っ走るために、機能主義的発想で人間に求めるものは使用価値であった。戦後は新しい憲法となったのであるが、この考え方は失われていないのである。
日本の官僚はそういう考え方を得意とするといってもいいが、機能主義的に使用価値のある人間が一番いい。このことは現在の会社ではその通りである。効率を追い求める世界では機能的に使用価値のある人間像が好ましいのである。だから日本は全体として効率を追い求める会社国家のさまを呈していると言えるかもしれない。(戦前は強制的使用価値的人間、戦後は強制はないが使用価値的観点は残った。)
2、近代の人間像にかかわる対照的二人
このやり方で近代化の人間像をした人物を生み出し描写したのは司馬遼太郎ということのようだ。よく言われる明るい近代日本の人間像である。一方でこうした機能だけで日本を作ることはできないと考えていたのは永井荷風であった。ヨーロッパは古臭い国だ。なんでも近代に解消できるものではない、という。
3、日本の近代から抜け落ちた使用価値のない人間
これはまさに私も経験したことであるが、会社人間としての使用価値がなくなると自分は人間でなくなったようにも感じる、あるいはそのように感じてひきこもる人もいると聞く。効率を追い求める体制というのは特に会社では著しいのであるが、使用価値がすべてである。それは国全体もそう考えている。だから使用価値がなくなると人間ではなくなるのである。
近代化という標語のもとに使用価値のある機能的人間を追求してきた日本だから、本当の意味での人間の尊厳、人格の重要性という考え方はなかなか頭でわかっても実感がない。人格の形成の重要性ということが切り捨てられた、といっても過言ではない。(大学での工学の優位性、文系不要論など)結局この使用価値に適合できないと感じる者たちはその社会から落ちていく。それがある人にはうつ病という病気になって発現する。現在うつ病が会社でも多い。
日本人にはそれでも欧米に追い付き追い越せででやってきた一流の賢さがあるが、どこまで行ってもそういう機能的に使用価値として人間をとらえてる限り、現在のように追いかけるターゲットがない時代の開発ということでは特に米国には負けてしまうのである。それは主体的人間の自発性、という重要な点が育てられないということにあるのではないか。
4、蛇足;先日の東洋スチレン、20周年記念のある社長のあいさつで
(2019、4,18、日比谷松本楼にて)
外人が従業員の半数になっており互いのコミュニケーションに非常に大きな問題がある、というようなことを言っていた。各国の文化理解は当然として人格としての人間を見る目が必要だ。機能と効率だけでは見えない。
この本ではそこまで言ってるわけではないが、結論的にそう感じざるを得ない。大方の人には異論のあるところでもあるだろう。(終わり)

