「ショックドクトリンー惨事便乗型の資本主義の正体を暴く」、上、下巻、ナオミ・クライン著、岩波書店、2011年発行2013年までに9刷、幾島幸子、村上由見子訳、原注までいれると760ページ。
この本の概略
この本は惨事便乗型資本主義複合体という視点で世界の政治、経済活動を切って見せた書といえる。ある意味グローバリズムの問題点を明確に描いている。著者30代の作品とは思えない力作である。
世界で起こっているショック型惨事、津波(日本やスリランカなど)、地震、テロ、局地紛争、民族紛争、イラク侵攻、民主革命(ソビエト崩壊、社会主義崩壊、南アのアパルトヘイトからの解放など)などに乗じて、その解決プロセスと称して、その地域の国民または民衆を相手にせず、グローバル資本(ほとんどアメリカ、イギリス)を投じて大きな利益を強奪していく戦略とその現実、帰結について書かれている。これだけ詳細な記述は私はまだ見ていない。
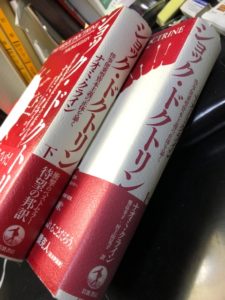
ミルトン・フリードマンの経済学説
惨事便乗型資本主義というのは、この中核になる思想というものがある。
これは、ミルトン・フリードマンという経済学者でノーベル経済学賞を受賞、特に米国を中心として1980年代にはシカゴ学派として知られている。彼の理論の概要については、本山美彦著「金融権力」(岩波新書)に詳しい。小さい政府というものを提唱。(この言葉は聞いたことがあると思うが)簡単に彼の理論を言えば強いものだけが勝ち残る資本主義というものである。競争の原理を生かし強いものが生き残る社会を理想としている。反政府、保険、教育、医療保険などの民営化、麻薬の放置等々、市場の力にすべて任せろという考え方である。現実的には拷問、虐待、戦争などを支持している。強いものが勝てばいいのだから。現実的には経済自由主義が通用しないのなら力づくでそれをやれという考え方であって、民衆のデモや抵抗運動を抹殺し関係者を監禁、拷問し、ショックを与えすべてを奪い取るというような恐るべき経済活動を支援する思想といってもいいだろう。
これが実施された国では悲惨な結果が待っていた。(この系譜に、ネオコン=新自由主義、ワシントンコンセンサス、IMFなど)
フリードマンからの直接の教え
南米の新興国、ソビエト崩壊から再建されなければらないロシア、ポーランド、中国など経済的な発展を希求している国々がこのシカゴ学派のミルトン・フリードマンの思想に大きく影響された。彼はこの種の国に呼ばれ自由な資本主義の概念を教えてきた。中国の登小平も同様に彼の改革の中核にはミルトン・フリードマンから直接受けた考え方がある。
米国政府の場合
もう一つこの本で言われている惨事便乗型というのはアメリカの政府にかかわる問題だ。アメリカ政府の高官、ディック・チェイニー、ロナルド・ラムズヘルド、J,Wブッシュ、キッシンジャーでさえこのシカゴ理論の信奉者で、民間の自分の関与しているビジネスの利益を誘導するような行動をしていることである。公務員法違反であるが、簡単にいえば惨事が起きる、あるいは起こすと、関係ある戦争・紛争ビジネスの企業群がーこの企業群にはセキュリティ関連、病院、ホテル、医薬部門などもある、ーその惨事を利用して惨事からの解決プロセスと称して、米国政府が中心となり本来であれば政府がしなければいけない仕事を外注化していく。例えばイラクの経済復興は会計事務所が法律を作り、運営までした。また民間が戦争請負をする。傭兵をかき集め軍事訓練をする。みんなこういうことを外注化するのである。外注化することによる大きな問題点がある。民主化されたプロセスを経ずに勝手にできる。外注先が安定した利益を得られれば政府関係者にも相当な利益として跳ね返る。個人的にも党としても。(その外注大手はハリ・バートン社など)
戦争(惨事)を好む人々
なぜ戦争が続くのか、戦争をしたい人がいる、それによって大きな利益を上げられる政府の関係者ー政府高官(を含む軍産複合体)であるが、特にアメリカではそのことが法的にも本来は許されないにもかかわらずうまく民間の利益となりその株をたくさん所有している人たち、政府高官(軍産複合体)の利益となる。結局政府と産業界のどちらにも同時に存在し関与することを当然視する状態が生まれた。特に最近は民間軍事部門への外注化、さらにセキュリティの外注化、軍の病院の外注化など政府の金を使って外注化へ拍車をかけている。民間には公務員の倫理感を求めようもないし政府を糾弾もできない。これらのいちいちが詳細ににここで述べられている。このことからイスラエルがパレスチナと平和を作り出すどころか悲惨なパレスチナ人を作り出していることの理由も分かるというものである。これは方向が変わったのである、と。城塞国家として他国からは外壁に守られた国として存立することにしたのである。全世界に起こっている惨事に便乗したビジネスでイスラエルはやっていけるという確信を得た。つまり対テロ工作、顔認証システム、ゲートチェックシステムなどお手の物である。イスラエル以上にこの分野で現実的な脅威を受けて対応している国はないのである。かつては中東のシンガポールを目指していたというのにである。
惨事便乗型の例
以前にも書いたことのある、南ア、ロシア、ポーランドという国々は、民主化を成し遂げてこれから経済の復興をしなければならないところにいたのである。この時にこのシカゴ学派の経済学者を送り込んで経済復興をしようとした。これが民衆の利益にならないどころか、政府の大事な国有資産であった国営の電話事業、鉱山事業、道路事業、保険、郵便、水道、その他政府のやっていた仕事を民間にほとんど売り渡す。安い価格で。それも外国資本。市場に任せる。それでロシアはオルガルヒ(成金億万長者)が登場した。あっという間に政府の資産は外国の資産に変り果てる。そのことによって改革前よりも一層悲惨な状態に国民がなる。労働者にいは恩恵がない。南アのアパルトヘイトでもそうだ。民主革命の闘士のマンデラの下これからは南アの黒人に土地所有権、きれいな水、食料を約束されていた、しかしオランダや、IMFやアメリカ、そしてワシントンコンセンサスというシカゴ学派の連携プレーでうまく宗主国のオランダに政府資産を乗っ取られてしまい、彼らの貧しさはアパルトヘイト時代よりもひどくなったという。(これは、日本との比較でいえば、実務官僚が広範に育っていない国であると言える。経済成長の仕組みを知って現実に適用する実務官僚の必要性を痛切に感じる。)
この本を読んで
日本と比較して考えると、経済史家の大塚久雄を思いだす。彼は国民経済の安定性が日本の独立を形成すると言っていた。彼の近代化論は国民経済学であるドイツのフリードリッヒリスト同様日本という国の自主独立を目指していた。産業の安定的な構成、中産的生産者層の確立のない国はこのような惨事便乗型の強欲資本主義の餌食となるのである。
この本は非常に長いので上巻だけでもいいかもしれない。後半は米国の政府高官と戦争外注化の関係というものとイスラエルの変質の追求である。具体的名前が挙げられており説得力に富む。
